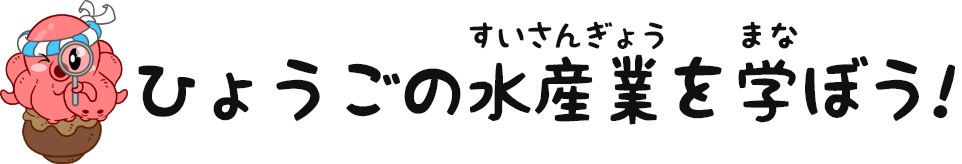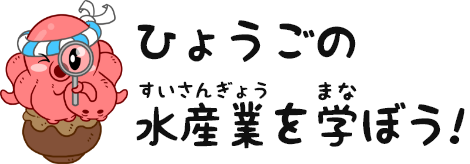古くから明石で獲られてきた水産物からランダムに10問出題します。
漢字の読み方をカタカナで回答してください。
沙魚
解説

秋が旬の魚で、播磨灘北部では生息域の関係で漁業対象にはなっていませんが、秋の休日には千種川や加古川などの汽水域ではハゼ釣りで賑わいます。
くせのない白身で、天ぷらから塩焼き、煮物、汁物など様々な調理法で食されます。
(写真提供:姫路市)
大口鰈
解説

ヒラメのこと。昔はヒラメもカレイと呼ばれていました。
全国に分布する高級魚の一つで、播磨灘では年間を通して底びき網やたて網漁で30~80cmのヒラメが漁獲されます。
晩秋から春にかけての低水温期が旬となり、刺身や昆布締め、あら煮、天ぷらなどで食されます。
(写真提供:姫路市)
鰆
解説

30~60cmをサゴシ、60~70cmをヤナギ、70cm~をサワラと呼ぶ出世魚です。播磨灘北部では、5~7月にかけて2隻の船を使って網で囲い込んで獲る”はなつぎ”と呼ばれる船びき網漁と、春から秋に行われる”ながせ”と呼ばれる流し刺網漁で漁獲します。
天ぷらや塩焼き、ソテーなど加熱料理に向いています。
(写真提供:姫路市)
鮧鱛
解説

ハダカイワシ目エソ科の海水魚の総称。アカエソ、オキエソなどがあり普通マエソを差しますが、播磨灘で見られるエソは主にトカゲエソです。
底びき網漁で混獲されますが、小骨が多く食べにくいことやまとまった量が獲れないことから市場にでることはほとんどありません。
(写真はトカゲエソ/写真提供:姫路市)
烏賊
解説

10本の足がある軟体動物です。厳密には8本の腕と、2本の触腕を持っています。
触腕はイカだけが持っている餌を捕獲するための特殊な腕で、伸縮自在で他の腕よりも長いのが特徴です。
明石海峡近辺では主にコウイカ、カミナリイカ、アオリイカ、ケンサキイカ等が漁獲されます。
(写真はコウイカ/写真提供:姫路市)
鰛
解説

ウルメイワシで、イワシの仲間です。20~25cmになり、播磨灘北部では、晩秋に船曳網漁や底引き網漁で混獲されます。
秋~春は脂が乗って美味しい魚ですが、鮮度の落ちが早いため鮮魚ではめったに売られていません。
(写真提供:姫路市)
鱠残魚
解説
シラウオのことも「鱠残魚」と書きますが、文献ではシロギスの地方名「キスゴ」のこと。播磨灘北部では主に底びき網漁で漁獲されます。
天ぷらや刺身、塩焼きをはじめ、様々な料理に利用できます。